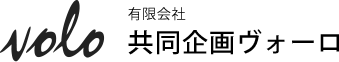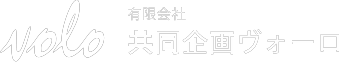2025.03.12
キネマNETで視聴できる作品をご紹介!~『雲ながるる果てに』編~
みなさん、キネマNET楽しんでいますか?
まだ会員登録していない方はこちらの記事を見てみてください。
今回ご紹介するのは、『雲ながるる果てに』という劇映画です。
舞台は昭和20年(1945年)の春、特攻隊基地の学徒兵たちの決意や葛藤を描いた作品です。
本記事を読んで興味を持っていただけましたら、ぜひキネマNETで『雲ながるる果てに』もご視聴ください。
目次
1.『雲ながるる果てに』はどんな作品?
2.そもそも特攻隊とは
3.『雲ながるる果てに』で印象深かったシーンをご紹介
4.まとめ
1.『雲ながるる果てに』はどんな作品?
『雲ながるる果てに』は、1953年に公開された家城巳代治監督の作品です。
この作品は、海軍飛行専修予備学生として出撃して亡くなった青年たちの遺稿集『雲ながるる果てに 戦歿飛行予備学生の手記』をもとにして作られました。
【あらすじ】
昭和20年春、特攻隊基地の学徒兵たちに特攻の命がくだるが、雨天や燃料不足などにより連日作戦が中止となった。
命を国に捧げる覚悟をした学徒兵たちは気丈にふるまうも、未練が付きまとう数日を過ごす。
やがて作戦実行の命が改めてくだされ、学徒兵たちは空に飛び立っていくのだった。
あらすじの通り、特攻隊を描いた映画です。
古い日本映画で映像も白黒ですが、それでも臨場感が漂う作品でした。
特攻作戦が延期され、いつまた特攻の命令がおりるのかわからない状況。
毎晩「明日が命日になるのでは?」と思いながら過ごす日々は相当こころに来るものでしょう。
学徒兵たちはそれでも思い出作りのためか、後悔しないためか、表向きは明るく日々を過ごします。
学徒兵たちのまっすぐな葛藤を描く一方で、軍の上層部の非情な側面も描かれています。
戦争や日本の未来について改めて深く考えさせられるような作品でした。
2.そもそも特攻隊とは
特攻隊を知らない方はいないかもしれませんが、ここでは改めて特攻隊について軽くご説明します。
特攻隊(とっこうたい)は、第二次世界大戦中に日本帝国海軍と陸軍が編成した特殊攻撃部隊を指します。
特攻隊は、特に1944年のレイテ沖海戦以降、戦局の悪化に伴い、米軍の艦船や輸送船に対して体当たり攻撃を行うために結成されました。
これらの攻撃は、「神風(かみかぜ)」とも呼ばれ、航空機や魚雷などを使用して行われました。
特攻隊は、燃料を片道分のみ積んだ航空機や魚雷に乗り込み、敵艦に突入して爆破するという戦術を取っていました。
この戦術は、特に米軍に対して大きな心理的圧力を与え、一部の艦船に深刻な被害をもたらしましたが、戦局を大きく変えることはできませんでした。
特攻隊の結成と運用は、日本の軍部が戦局の絶望的な状況を打開しようとした結果であり、志願制が基本とされましたが、実際には強制された場合も少なくありませんでした。
特攻隊員の多くは若者でした。戦局が厳しくなると共に多くの命が失われていきました。
3.『雲ながるる果てに』で印象深かったシーンをご紹介
この映画を見て一番初めに思ったのは、学徒兵たちの感情の起伏が激しいということでした。
命をささげる覚悟をしているのですから、それもそのはずです。
この映画では、
「特攻の命令が下る」→「最後の思い出作りにどんちゃん騒ぎ」→「作戦中止」→「また特攻の命令が下る」→「最後の思い出作りにどんちゃん騒ぎ」→「作戦中止」
という流れで学徒兵たちを描いており、大まかに言ってしまうとシリアスなシーンとガヤガヤしたシーンが交互に来るような作りになっていました。
この場面の雰囲気の豹変具合から若さを感じるとともに、楽しそうに宴会をする姿がむなしいものにも見えてしまい、終始戦争の残酷さを感じました。
また、作中では国のために命をささげることが正義だと疑わない学徒兵が終盤には戦争に懐疑的になったり、上層部から消耗品だと思われていることを自覚しながらも散る覚悟を決めていたりなど、学徒兵から漂う無力感も感じられました。
最後のシーンでは、戦闘機が次々と墜落していく映像と、その模様がモールス信号で伝えられる場面が交互に流れるのですが、信号が途切れたときに上官が放った言葉が忘れられません。怒りを通り越して恐怖を感じました。
改めて、「戦争とは何か」ということを突き付けられたようでした。
4.まとめ
今回は、『雲ながるる果てに』という劇映画についてご紹介しました。戦争映画は好き嫌いが分かれるジャンルだと思いますが、毎日おいしいご飯が食べられる今だからこそ、見てほしい作品です。
キネマNETはこちら(https://kinemanet.jp/)